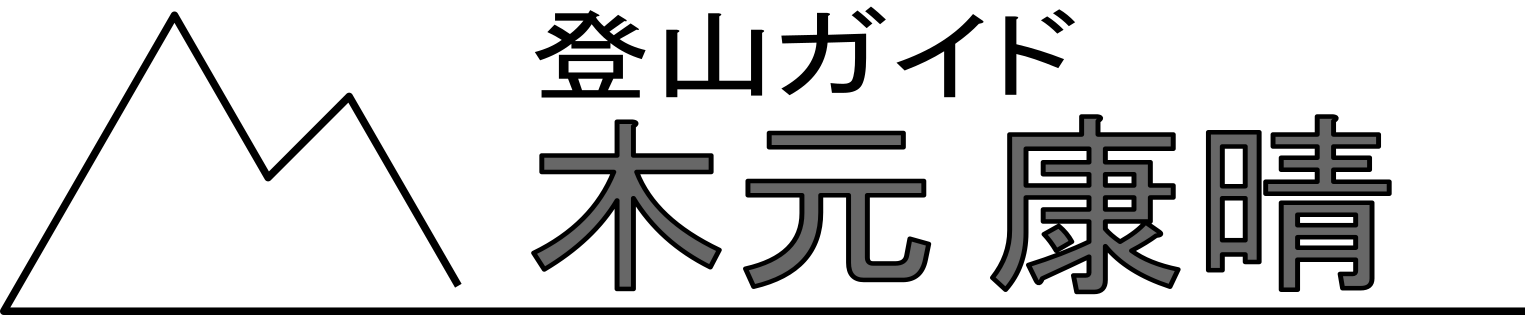フリークライミングのはじまりを知る一冊。
『クライミングジャーナル』編集長の著書
私が登山やクライミングに取り組み始めた頃に、発売日を心待ちにしていた雑誌があります。それは白山書房から出ていた、今はなき『クライミングジャーナル』でした。写真を大きく扱った見て楽しめる誌面だったことに加え、ルート紹介の記事が豊富で、登ってみようと触発されることが多かったからです。1991年5月に休刊となったときには、寂しい思いがしたものでした。
その『クライミングジャーナル』の編集長だったのが、菊地敏之。1982年1月に、当時登ることは不可能ではないかと言われていた、谷川岳一ノ倉沢の烏帽子沢奥壁大氷柱を初登した、実力派クライマーでもある人です。
菊地氏は編集長ながら、誌上に数多くの記事を書いていました。いずれも主張が明確で、読んで納得するものばかり。その中でも私が特に楽しみにしていたのが「実践アルパイン・クライミングテクニック」という連載記事でした。豊富な実体験を取り混ぜた実用的な技術解説であり、ここに書かれていることを頭に叩き込んで、せっせと岩場に向かったものです。
そういった解りやすさに定評があるからでしょう、菊地氏の著書は技術解説書が多いのですが、2004年には傾向の違う本を出版。それは『我々はいかに「石」にかじりついてきたか ――日本フリークライミング小史――』というもので、菊地氏が谷川岳など山岳地帯の岩壁でのロッククライミング(いわゆるアルパインクライミング)とは別に力を注いできた、フリークライミングについて記した本です。
今は各地にクライミングジムも多く、とてもポピュラーになったフリークライミングですが、国内で行われるようになったのは比較的日が浅く、40年ほど前のこと。菊地氏は手探りで始まったその時期からフリークライミングに取り組んでいて、この本ではその流れを伝えています。

カオスでアナーキーだった時代
この本でまず驚いたのは、「有史以前のボルダリング」という章に記される、1970年台の三浦半島・鷹取山の岩場の様子です。鷹取山は古くからアルパインクライミングの練習場ではあったのですが、それとは異なる、現在と同様のボルダリング(あまり高くない岩場でのロープを使わないフリークライミング)が、その頃から自然発生的に行われるようになっていたとのこと。フリークライミングの概念がない時代に、単に難しい壁面を登るという行為に魅力を感じる人たちが、すでに存在したというのは興味深いことでした。
その後1980年台に入り、アメリカのヨセミテの動向が国内にも伝わってきて、菊地氏をはじめとするクライマーたちも本格的にフリークライミングに取り組むことになります。
ただし、実際に取り組んでみると解るのですが、フリークライミングでレベルアップするのはなかなか困難なこと。普通の趣味のように、月に2~3回やる程度では、上達はあり得ません。したがってどのクライマーも、ろくに定職に就かずに、ひたすらクライミングに打ち込むことになります。
けれども当時の多くの一般人は、フリークライミングなんて野蛮で危険なだけの行為と思っていたに違いありません。クライマーたちはある意味社会に背を向けるようにして、レベルアップを目指し突き進んでいったのです。そしてフリークライミングそのものも、まだまだ発展途上。次々と新しいスタイルが試みられ、混沌とした状況が続きます。
この本は、そうやって次第に形作られていくフリークライミングの世界と、試行錯誤を繰り返すクライマーたちの姿が書き綴られた、貴重な一冊です。とは言ってもけっして堅苦しさはなく、菊地氏ならではの毒のあるユーモア溢れる文章は楽しくて、読んでいるとつい笑いがこみ上げてきます。
今やフリークライミングは、2020東京オリンピックに「スポーツクライミング」として正式採用されるほど、成熟しました。公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会のウェブサイトで見る、強化選手の面々は、正にスポーツ選手を思わせる爽やかな健全さ。
しかしひと昔前の、非常にワイルドだったフリークライミング本来の姿を知ることで、より深くこのスポーツの魅力を知ることができるでしょう。これからフリークライミングに取り組んだり、競技を観戦しようとする人には、ぜひ一度読んでみてほしい一冊です。
(『週刊ヤマケイ』2018年5月24日配信号に掲載)