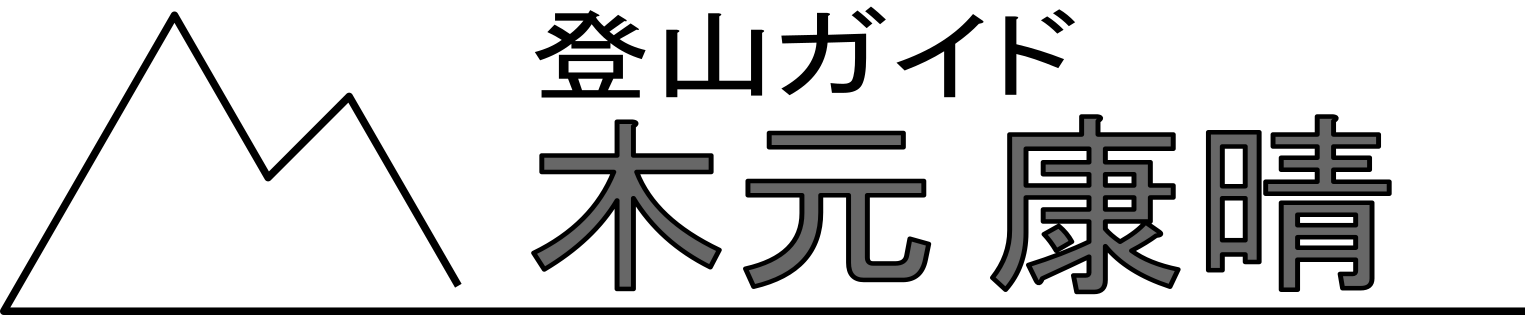ポジティブに高みを目指し続ける山野井泰史。
ずっと応援し続けてきた登山家
日本の重要な登山家を挙げる場合に、絶対に欠かすことができない一人が山野井泰史でしょう。53歳になる現在も登る意欲はまったく失われていないようで、つい先月も、ひどい顔面凍傷を負いながらも北海道の上ホロカメットク正面壁を登ったとのこと。
私が山野井氏の名前を知ったのは、1990年頃に出ていた雑誌『クライミングジャーナル』の誌上でした。その43号の特集記事「世界のビッグウォール」の冒頭にあったのが、パタゴニアの岩壁に向かうという山野井氏のインタビューだったのです。そのときはクライミングに取り憑かれたような人だな、くらいの印象だったのですが、その後『岩と雪』に時おり掲載される山野井氏の山行記録を読むにつれ、これは物凄い人物だとうならされました。パタゴニアの岩峰フィッツロイ、ヒマラヤのアマダブラム西壁、チョー・オユー南西壁と、数年ごとにより困難な登山を、しかも単独で成功させていく様子には、圧倒されたものです。
そしてそれらの記録を読むうちに、いつしか私は大の山野井ファンとなり、陰ながら声援を送り続けるようになったのです。
その山野井氏を追った人物ルポ『ソロ』が『山と溪谷』に連載され始めたのは、90年台の後半の頃。しかし著者の丸山直樹氏が、以前『岳人』に連載していた遭難を分析する記事は、あまりにも辛辣過ぎるものでした。山野井氏に対しても、同様の辛口の批判を展開するのではないかと、一抹の不安も感じていました。
ところが始まった連載は、時おり心ない記述も目に付いたものの、最後まで読み終えると、山野井氏を理解し讃えあげる、爽やかな読後感を残す内容にまとめ上げられていたのです。「品位」や「善性」といった言葉が散りばめられた最終回では、思わず感動してしまいました。

山のすべてを受け入れて登る
登山界では知らぬ人はいない山野井氏ですが、ご本人がメディアに出ることにさほど積極的ではないためか、実績の割には知名度は低めかもしれません。多くの一般の人が山野井氏の名前を耳にしたのは、主に2つの出来事によるものではないでしょうか? そのひとつは2003年の秋、世界第15番目の高峰であるギャチュンカンを北壁から登り、その下山中に悪天候に遭遇し重い凍傷を負ったこと。この経緯はノンフィクション作家の沢木耕太郎氏が、入念な取材のうえまとめ上げた『凍』という本に詳細に記されて、話題になりました。
そしてもうひとつは2008年の秋、テレビのニュースでも報道された、奥多摩山中の自宅近くで山野井氏がツキノワグマに襲われた事故です。
山での危険はできる限り排除したいものですが、ゼロにするのは不可能なこと。特に山野井氏のように山に向かう日数が非常に多いと、それに比例して危険に出くわす確率は増えます。上に挙げたギャチュンカンでは、雪崩に遭遇するなどして下山は困難を極め、凍傷に侵された手足の指10本を切断することに。またツキノワグマに襲われたときには、顔と腕とで合計90針も縫う重症だったのだそうです。
さらにこの2件以外にも、山野井氏は落石を受けたり、墜落をしたりで繰り返し大ケガを負っているのです。
ところが、ギャチュンカンのことを記したご自身の著書である『垂直の記憶』や、『凍』を読んでも、危機的状況に陥ったことに対する、否定的な記述はありません。描かれているのはむしろ、絶望的な状況下であってもギリギリのリスクマネジメントを行い、生き抜くために最大限の努力をする姿です。悲惨なビバークを繰り返しつつ迎えた、ベースキャンプに帰着する最後の朝の、
おまえがベースキャンプにたどり点けなかったら、すべて終わりだ。(中略)無理な動作はやめろ。最後まで命の炎を燃やそう。
『垂直の記憶』
という独白からも、強烈なまでのポジティブさが伝わってきます。
そのことは近著である、『アルピニズムと死』からも感じます。この本はタイトル通り、山での死について書いた本ではあるのですが、暗さはなく、山での危険や困難や苦痛までをも含めて、山に登ることに対してのポジティブさが感じられるのです。
中学生の頃には、登山一筋で生きることを決めていたという山野井氏。後悔のないよう、妥協せず、深く考えて登りたい山を純粋に目指していくその姿は見事です。これら一連の山野井氏の本は、自分のやりたいことを貫き通して生きるとはどういうことかを伝える、人生の指南書としても読むことができる、重みのあるものだと思えるのです。
(『週刊ヤマケイ』2018年4月26日配信号に掲載)