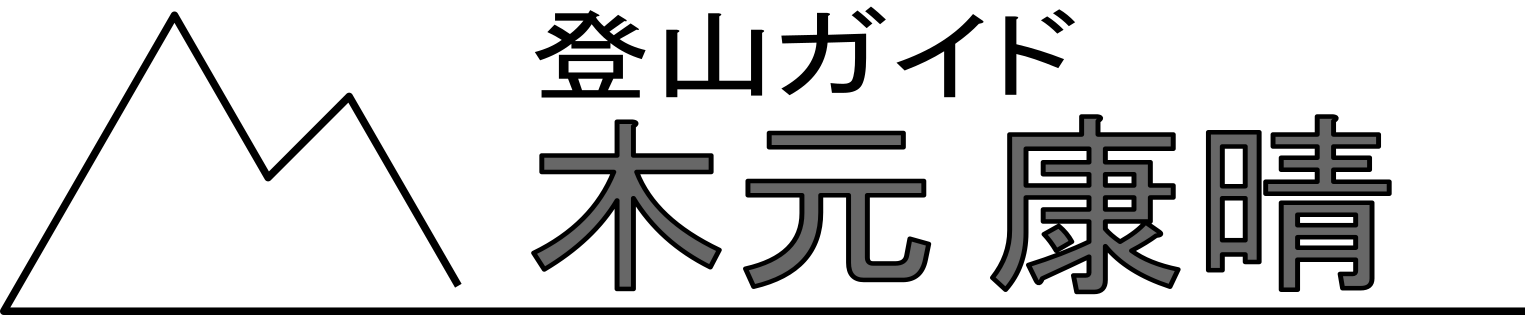北アルプスとベトナムで同時進行する壮大な物語。
会長の勧めで入手した小説
「なにか来る…大勢でお父さんを殺しに来るよ」
暗闇の中でゆっくりと顔を上げる少女がこのようにつぶやく、かなりインパクトのあるテレビのCMを覚えている人は、私と同年代以上では多いのではないでしょうか?
このCMは、70年代後半から80年代にかけて一世を風靡した角川映画のひとつ、『野生の証明』の予告編です。公開時は私はまだ小学生で、特に興味は持たなかったのですが、その後中学1年生のときにテレビ放映を観て感動。過激な暴力シーンに背筋が凍りついたものの、主役である高倉健の格好良さに惚れ惚れとしたものです。それと同時に、田舎の殺人事件が国の謀略を暴き出すことに結びつく骨太のストーリーには、子供ながらに凄いと感じさせられました。
この映画には原作本がありました。著者は、推理小説作家の森村誠一です。映画の印象が鮮烈だったので、その骨太のストーリーをもっと深く知りたいと考え、お小遣いを使って購入し、一気に読み終えました。映画のような派手なアクションシーンはなかったもののこちらも非常に面白く、以降は森村氏の小説を次々と読みふけることに。これらには凄惨な殺人場面や官能描写も混じっているためか、父親には、
「中学生の読む本じゃないぞ!」
と小言を言われたりもしましたが、右から左へ聞き流して、気の向くままにあれこれ読んでいました。
それから10年以上経った頃、山岳会の飲み会でのことです。隣に座っていた会長が、
「木元、お前は山の小説は読むのか?」
と声をかけてきました。新田次郎は一通り読んでいて、中でも『銀嶺の人』が好きだと答えると、
「新田次郎もいいがな、山の小説で一番面白いのは森村誠一だよ」
と言うのには驚きました。以前は私も森村氏が好きだったものの、本格的な山岳小説とは無縁の大衆向けの作家、という印象を抱いていたからです。森村氏のどの作品が面白いのか会長に聞くと、
「『青春の源流』だよ。一度読んでみろ」
という返事。私が読んでいないものでした。会長の勧めを無視できず、古書店をあちこち探し回り、入手したのはそれから3ヶ月くらい経ってからだったと思います。

森村誠一が書く山岳小説とは?
この『青春の源流』の物語は、1943(昭和18)年の9月から始まります。不足する兵員を補うための学徒動員が開始された時期で、物語の主人公である逢坂慎吉と楯岡正巳の二人は、3ヶ月後に控える入営を前に、大好きな北アルプスの姿を心に刻み込もうと、雲ノ平や裏銀座を巡り歩いていたのでした。
その当時の日本の戦局は惨憺たるもので、入営後に例えば南方行きとなった場合の生存率は、20%くらいだったそうです。かといって兵役拒否すると、非常に厳しい罰則が待ち構えていたために、どれだけ嫌であっても、兵役には応じざるを得ない状況。
しかし逢坂はその兵役を拒否し、取り締まりの憲兵が追ってくることが困難な北アルプスの奥地に逃げることを決意。当時は高天原に鉱山小屋があったため、戦争が終わるまでそこに隠れ住むことにしたのです。
それに対して楯岡は、家族にまでも迷惑がかかる兵役拒否はできないとして入営。その後間もなく、見習士官としてベトナムへ送り込まれたのでした。
やがて2年が経過し、終戦を迎えます。無事に隠れ通した逢坂は、戦争中に荒廃した三俣山荘の経営に着手することに。一方の楯岡は、帰国のタイミングを失ってベトナムにとどまり、ベトミン兵の一員としてフランス軍との戦いに身を投じることになってしまったのです。
以降は北アルプスとベトナムの、まるで関連のない話が同時進行するのですが、まったく違和感を感じさせない、読み応えのある展開で物語は進みます。逢坂が山への情熱を燃やし、三俣山荘を復旧させるだけでなく、ヒマラヤ登山を志すのも興味深いのですが、それにも増して楯岡が、旧日本軍で身につけた戦術を駆使して、フランス軍を打ち破っていくのは迫力満点。そして森村氏の本領を発揮した推理小説の要素もふんだんに盛り込まれており、複雑に張り巡らされた伏線が物語の後半で一気に収束し、力強くまとまったストーリーを形作っていくのは圧倒的です。
本当に心から、読んで良かった!と思えた小説であり、勧めてくれた会長には今も感謝しています。
ちなみに私の一番のお気に入りの場面は、物語の序盤で重要な役割を果たす、2匹のウサギの登場シーン。動物好きの私は、中でもウサギが大好きなので、読んでいて胸が熱くなりました。
なおこの小説とオーバーラップする戦後の三俣山荘については、逢坂のモデルとなった伊藤正一氏の著書『黒部の山賊』に詳しく記されています。こちらも併せて読むと、『青春の源流』をより深く楽しめるでしょう。
(『週刊ヤマケイ』2018年2月1日配信号に掲載)